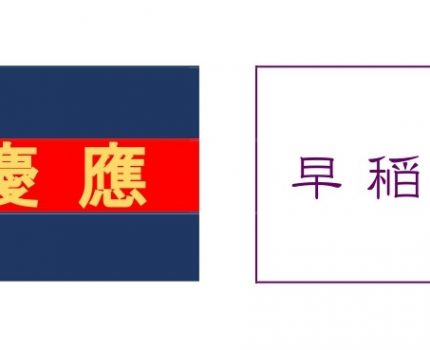2019年秋の東京六大学リーグ戦は慶應義塾大学が18年春以来、3シーズンぶりの優勝を決めた。だが早慶戦は2勝1敗で早稲田が意地を見せて「勝利」した。早稲田の小宮山悟監督は「早慶戦でふがいない試合をするわけにはいかない」とコメントしたそうだが、この意見を素晴らしき伝統と好意的にとらえるか、内輪のお楽しみと冷ややかに見るかは分かれるところだろう。個人的な感想を言うと小宮山監督は先進的な考え方を持っている指導者と思っていたが、意外にコンサバなんだなと。
 ともあれ、これまでの早慶戦を振り返ると、対戦成績は2019年春までに早稲田の230勝191敗10分と、100余年を経て「挑戦状」をたたきつけ、早慶戦開始のきっかけを作った、後輩格の早稲田が差をつけている。リーグ戦優勝回数も早稲田がリーグ最多の45回に対して、この秋の優勝で慶應は37回となっている。
ともあれ、これまでの早慶戦を振り返ると、対戦成績は2019年春までに早稲田の230勝191敗10分と、100余年を経て「挑戦状」をたたきつけ、早慶戦開始のきっかけを作った、後輩格の早稲田が差をつけている。リーグ戦優勝回数も早稲田がリーグ最多の45回に対して、この秋の優勝で慶應は37回となっている。
早稲田優勢の理由はどこにあるのか? 一つには両校の選手集め差があるだろう。スポーツ科学部を有する早稲田がスポーツ推薦で全国から優秀な選手を集めているのに対して、慶應はアスリート能力に偏重せず、あの江川卓が、入学を熱望したものの情け容赦なく不合格にしたように一定の学力水準を求めて、表向きスポーツ推薦は行っていない。
例えば1985年、PLの優勝投手、桑田真澄は早稲田大学進学を希望した。結局、合格不合格の以前に、桑田は願書すら出さず、巨人入りのダシに使ったため、早稲田は激怒することになるが、「希望」した時点で入学は内定したかのようだった。「ハンカチ王子」こと斎藤佑樹も系列校である早稲田実業出身だが、こちらもすんなりと入学した。現在も過去も、一定の推薦枠を持つとされる早稲田は斎藤のほか、八木沢荘六、三澤興一といった甲子園優勝投手をはじめ高校野球のスターが多数いるが、慶應は1995年夏の準優勝投手、山本省吾がいるくらいで、甲子園で目立った活躍をした選手はあまり見当たらない。
ただ慶応もまったく選手集めをしていないわけではなく、AO入試や指定校推薦で野球強豪校の選手が入部している。さらに慶應といえば「内部進学」だが野球部でもその傾向強く、系列校出身者のうち大部分を占める高校野球の激戦・神奈川県の強豪、慶應高校からの入部も多い。この慶應式「内部進学」がちょっとしたからくりになっており、2013年にドラフト6位で日本ハムに入団した白村明弘は岐阜県出身で中学時代は岐阜中央シニアでプレーし慶應高校に進学後、内部進学で入部してきた。2019年のドラフトで楽天3位の津留崎大成は千葉県鎌ケ谷市出身で佐倉シニアで頭角を現し、小学6年時に千葉ロッテJrでプレー。慶應高校、大学へと進んだ。ソフトバンク5位の柳町達は茨城県出身で中学時代に取手シニアで2年時全国優勝、3年時全国準優勝、慶應高校に進学し内部進学で入部している。実は内部進学のように見えて、中学段階で「スカウト」された有力選手がいるというわけだ。
こういった慶應の「戦力補強」の効果が出てきたのか、2015年から2019年までの5年間10シーズンの早慶戦の対戦成績は早稲田の15勝12敗、優勝は慶應3回で、早稲田の2回と拮抗している。70年代中盤以降、じわじわと早稲田が差をつけリードしてきたが、慶應も過去3年6シーズンで3度の優勝とリーグ戦の結果を見れば地力をつけており健闘しているといっていいだろう。
(「屁理屈野球雑記」石川哲也)